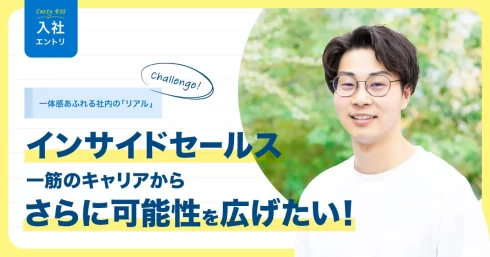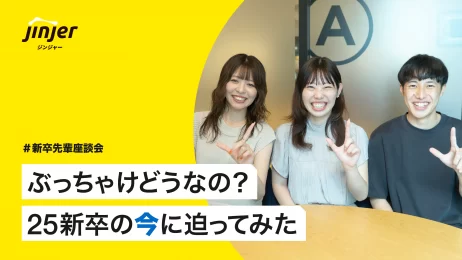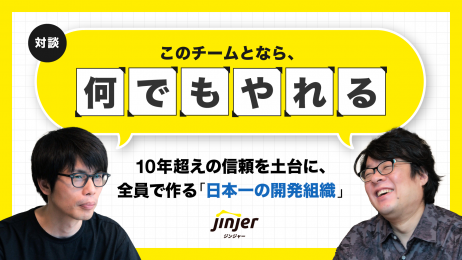jinjerは今、事業の急成長と共に開発組織の拡大フェーズにあります。今回は、プロダクトと技術の両面から開発チームを牽引するVPoTの山田さん、そしてテックリードである福与さん、安東さんの3名に、「日本一」を目指し、「自分ごと」として「バクソク開発」を突き進むjinjerの開発チームの面白さについて話を聞きました。
プロダクトの成長を支え、未来を築くテックリードたち
――まずはお三方の役割について教えていただけますか?
山田: 私はVPoTとして、jinjerの開発組織全体を見ています。具体的には、「ジンジャー給与」、「ジンジャー人事労務」を担当しながら、開発部の技術選定など、各所でリーダーシップを取る立場です。「日本一」の開発組織を目指す上で、技術とプロダクトの両面からチームを牽引しています。
福与: 私は現在、「ジンジャー勤怠」を担当しています。また、全体的なアーキテクチャや技術的な部分を見つつ、以前は「ストラグ」というチームでジンジャー全体に共通するログ基盤などの仕組みを横展開していました。あとは、勉強会などを通したエンジニアの人材育成も担当しています。
安東: 私の担当は「ジンジャー給与」がメインで、一部「ジンジャー人事労務」も見ています。役割は福与さんとほぼ同じで、アーキテクチャやログ基盤の設計、新しい開発基盤の構築を担当しています。

※写真:(左)山田さん、(真ん中)安東さん、(右)福与さん
――プロダクトが多い中で、複数のテックリードがいらっしゃる理由はなぜでしょうか?
山田: テックリードという明確な役割が最初からあったわけではないんです。私を含めたこの3人は、もともと”開発基盤チーム”として動いていました。その中で、技術的な課題解決に深く携わるうちに、自然とテックリードとして動くようになったという形です。
福与: 開発基盤チームは、ジンジャー全体の基盤における課題解決を目的として発足しました。開発基盤の統一やレガシー部分の刷新に取り組む中で、「日本一」のプロダクトとして昇華させ、その基盤を支えるために、自然と開発全体を牽引する役割を担うようになりました。
jinjerを選んだ理由:自社サービスへの憧れと内製化への共感
――お三方がjinjerを選んだ理由についてもお伺いしたいです。
福与: 私は現在51歳ですが、いくつになっても「現場で技術者として活躍し続けたい」という想いが一番にあります。メンバーのマネジメント業務より、いちエンジニアとしてプロダクト開発に取り組むことに、やりがいと楽しさを感じます。前職では受託開発が多かったので「自社サービスの開発に携わりたい」という気持ちも強くありました。自分の意見がサービスに反映され、世の中の役に立てることに、ある種の憧れを抱いていました。
安東: 私も前職はSIerで、受託開発が中心でした。jinjerを知ったのは、前職でジンジャーを使っていたのがきっかけです。使ううちに「ここを改善したらもっと良くなるのに」と勝手に考えていたんです。
その後、転職活動中に偶然jinjerがエンジニア採用をしていることを知り、応募しました。その際、CTO高村さんやVPoE山本さんと話した時に「これは楽しそうだ」と感じて、入社を決めました。「自分ごと」としてプロダクトを良くしていきたいという想いが強かったですね。
山田:私もこれまでのキャリアで、ベンダーの立場で仕事をしてきました。その中で、顧客とベンダーの最適解が必ずしも一致しないことに違和感を覚えていたんです。このギャップを埋めるには、事業会社の中に入って、「自分ごと」として開発に深く携わることが必要ではないか、という仮説を自分の中で立てていました。
そんな時、CTO高村さんやVPoE山本さんから声をかけてもらい、彼らが掲げる「日本一を目指す」というビジョンにも強く共感しました。ここでなら、自分の仮説を検証し、「本当にユーザーにとって良いものを作れる」と感じたので、jinjerを選びました。

ーー自社サービスを持つことへの「憧れ」が共通しているようですが、これはエンジニアの皆さんに共通する感覚なのでしょうか?
安東:そうですね。特に私たちのようなSIer出身のエンジニアには、同様の想いを持つ人が多いような気がします。あくまでもお客様のサービスを作るので、良くも悪くも”言われたものを作る”側面が強いです。
自分たちで「こうしたらもっと良くなる」という意見があっても、反映できるのはお客様の判断次第です。だからこそ、「自分で自社サービスを作っていきたい」という気持ちは、SIer出身のエンジニアには特に強いと思います。
成長フェーズとカオスを楽しめる組織
ーー山田さんから見て、今、jinjerのプロダクト開発はどのような成長フェーズにあるのでしょうか?
山田: プロダクトによって異なりますが、タレントマネジメント領域はまさに新機能をどんどん作り、事業を伸ばすフェーズです。「ジンジャー人事労務」や「ジンジャー勤怠」といった核となるプロダクトは、PMFをさらに深め、使いやすさを磨き上げていく段階になります。どちらのフェーズにせよ、機能開発をどんどん進めています。
開発組織としては、今まさに組織拡大のフェーズにあります。これまで外部ベンダーに頼っていた部分を「内製化」するべく、積極的にメンバーを増やしています。
正直、まだ整備されていない部分もありますが、それをコントロールしながら、皆が「自分ごと」でプロダクト開発ができる組織になっていく。そういう意味では、すごく面白いフェーズだと思っています。このカオスを楽しみながら、「バクソクで各プロダクトの開発」を進めていけるのが今のjinjerです。
日本一を目指す開発基盤設計:妥協のない熱い議論とスピーディーな反映
ーー開発基盤の構築はどのように進められたのですか?
山田: マインド的な話で言うと、常に「これは日本一と言えるのか?」という問いのもと、開発基盤を構築しています。現状で「日本一」と言えないなら何が足りないのか、常に考えながら取り組むことに大きな価値があります。
例えば以前は、問題発生時にログが不十分で原因究明が難航していました。プロダクトごとにバラバラだったログの構想を、まずジンジャー全体で統一しようという話から始まったんです。
福与: ログがないと調査ができませんし、ユーザー様にもご迷惑をかけてしまいますからね。ログ基盤をどうするか、3人で長時間議論しました。
導入のしやすさと調査のしやすさを軸に、いかに簡単に導入してもらい、どう作ったら調査しやすいか。この2点に重きをおいて議論を進め、結果的に「Athena」というAWSのサービスを使ってログ集約を成功させました。
ここで大事なのは、全員が納得いくまで徹底的に議論することです。これは開発チーム全体の特徴でもあると思います。時には白熱しますが、それは「皆で多角的に問題を理解し、解決策を見つけるため」。新しく入社した人でも、遠慮なく意見を言え、皆で議論し、考えられるメンバーが多くいます。
安東: 福与さんと私は、よく議論の場で言い合いになることもありますが、ミーティングが終われば何事もなかったように二人でコーヒーを飲みに行きます(笑)
お互いに違う視点から疑念を持ち、妥協せず意見をぶつけ合うことで、最終的にプロダクトやエンジニアにとって「日本一」に繋がる良いものが生まれると信じています。

シリーズ展開を見据えたアーキテクチャの進化:10年後も使える基盤を
ーーアーキテクチャの話についてもお伺いしたいのですが、どのように変化していったのでしょうか?
山田: シリーズ展開を視野に入れたアーキテクチャの進化には、いくつか重要なポイントがあります。
①「横断的に解決できること」
②「導入の容易さ」
③「エンジニア体験の向上につながること」
④「10年後も利用可能な基盤であるか」
これらのポイントに重きを置いていますが、その最後の問いかけとして私が最も重視しているのが、
⑤「日本一と言えるレベルにあるか」
これらの要素を追求することで、強力で適応性の高いアーキテクチャを構築できると考えています。
福与: アーキテクチャを進化させるのは、基本的に現状に問題があるからです。
コードが複雑でメンテナンス性が落ちている場合は、そもそも複雑にならないようなアーキテクチャの構成を考えます。今はモジュラーモノリスやクリーンアーキテクチャを導入して、分かりやすくしています。
安東:各アプリケーションには成長の過程があり、ジンジャーもより大規模な従業員数に耐えられるよう、アーキテクチャを見直すことが頻繁にあります。不具合やパフォーマンス劣化につながる部分に関しては、積極的にアーキテクチャを変えていくことが非常に重要です。常にアップデートし続けるイメージですね。
山田: 私たちは、解決したい課題があれば、それがアーキテクチャを直すべき問題であれば、問題の先送りはせず、真っ先に解決のために動きます。
技術選定においては、流行りにとらわれず「今の私たちに何がベストか」を考え抜きます。古いものでも、新しいものでも、最善なら選びます。技術的負債も発生するものなので都度直しますが、ただの「もぐら叩き」ではなく、横断的に「こうあるべきだ」という理想を掲げて、そこを目指していきます。
横断的に全体を見る視点と「自分ごと化」カルチャー
ーー横断的に物事を見るってなかなか難しいと思うのですが、皆さんはどう考えて行動に移しているんですか?
安東:私の場合、山田さんや福与さんといった圧倒的に技術的知見が高い人たちが近くにいるので、彼らの背中を見ながら動いてきました。彼らにはまだまだ敵わないので、壁打ちをする感覚で、自分のアイデアをガンガンぶつけにいくことが多いですね。
山田: 安東さんは「足を使う人」だと思います。分からないことがあれば積極的に聞きに行く。情報収集能力が高いので、横断的に見る素質があるのでしょう。福与さんはどうですか?
福与: 私は打ち合わせなどで「こういう問題がある」「ここがやりづらい」といった話をよく耳に留めておくようにしています。それを解決することで、他のプロダクトも楽になるんじゃないか、という視点です。山田さんからも「ここで作ったものが横展開できるかどうか」を常に意識するように言われています。今のプロジェクトだけでなく、他のプロダクトでも横断して使えるようにと考えて作っています。
山田: 私の場合は、まずVPoTというポジションですね。組織全体を見ているため、そもそも横断的な課題や共通項を見つけやすいのだと思います。
また、情報収集も怠らないようにしています。安東さんや福与さんが開催してくれる勉強会で、PMやエンジニアからの情報を得ています。
ただ根本にあるのは、単純に幅広い領域の課題解決が好きだからです。jinjerに入社した理由も、「自分のプロダクトを最大限大きくしたい」という想いがあったので、局所的な課題解決だけでは意味がないと考えています。これら全てが、「自分ごと」として開発を行い、プロダクトを成長させたいという想いに繋がっています。
jinjerでしかできない経験:「バクソク開発」と「背中で語る」文化
ーー最後に、jinjerで働くことでしかできない経験や、一緒に働くと面白い理由について、お三方の観点からそれぞれ教えてください。
安東: やはり「風通しの良さ」と「距離感の近さ」ですね。開発部内は特に雰囲気が良く、他部署からも「開発チーム本当に仲良いよね!」とよく言われます。また、CTO、VPoEなどトップへの話のしやすさも、前職と比べても全然違います。
山田: 安東さんの話に付け加えるなら、意思決定から対応までのスピード感です。
例えば、安東さんが「これが良いと思うからこうしませんか?」と提案した時に、「それいいね」となれば、当日か翌日にはもう動き始めているんです。もちろん、皆が納得できない意見であれば動きませんが、「いけるね」となった瞬間に動き出す。このスピード感が、風通しの良さや距離感の近さに繋がっていると思います。
ーー提案したものがすぐに動き出したエピソードって何かありますか?
安東: 無限にありますね(笑)。特に昨年は3人で開発している期間が長かったので、頻繁にありました。例えば、ログを収集するデータの構成について、「こんな感じにしますか」と話して、結論が出たらすぐに動いていました。
他にも「フロントエンドの開発リソースが足りない」という話が挙がった時、すぐにリソースを調整して「来週からこの人がサポートで入ってくれるから、それまで準備しよう」といったことがありました。このレベルで、皆の意見をどんどん出してもらって、良いと思ったらすぐにやる、という感じです。
福与: 今の段階で言うと、ここ1年でエンジニアが増えてきて、組織がより良くなっている過程にあるので、jinjerの「日本一」に繋がる良いスタンダードを、今まさに作っている実感があります。
山田: お二人のお話がほぼ全てを言ってくれたのですが、付け加えるなら私は「自分ごと化」がものすごく大事だと思っています。
「自分ごとで開発ができる、しかもバクソクで開発ができる」。エンジニアとして、これは本当に楽しいことだと思いますし、jinjerでしかできない経験じゃないでしょうか。主体的にやっていいよ、という会社はたくさんあると思いますが、「意思決定を含めてバクソクでできている組織」は、なかなかレアだと思いますね。

まとめ
今回の対談では、jinjer開発組織の「日本一」に対する飽くなき追求と、「自分ごと」として「バクソク開発」を推進する文化が、とくに印象的でした。
山田さん、福与さん、安東さんは、ログ基盤やアーキテクチャの構築・進化において、常に「これは日本一と言えるか?」と自問自答し、妥協なき議論を重ねています。その背景には、ユーザーへの価値提供とエンジニアの働きやすさ向上への強いこだわりがありました。
特に印象的だったのは、良いアイデアが浮上すればすぐに形になる「バクソク開発」のスピード感。これは、「自分ごととして自社サービスを作りたい」という強い想いを持って集まったメンバーにとって、まさに理想的な環境です。技術的負債にも臆することなく、最適な技術を柔軟に選択していく姿勢は、持続可能な成長を目指す”jinjerのDNA”とも言えるでしょう。
事業の急成長と共に組織も拡大中のjinjerでは、挑戦に満ちた環境でプロダクトを「自分ごと」として動かし、大きな裁量とスピード感を持って開発に携われます。私たちは、この熱い環境で共に「ジンジャー」の未来を創造していく新たな仲間を求めています。