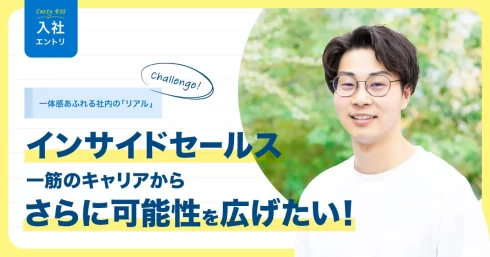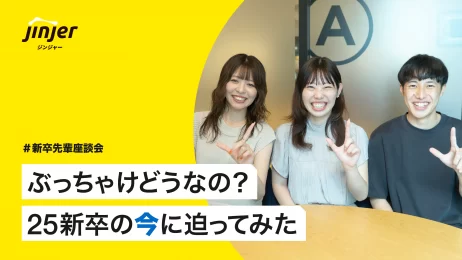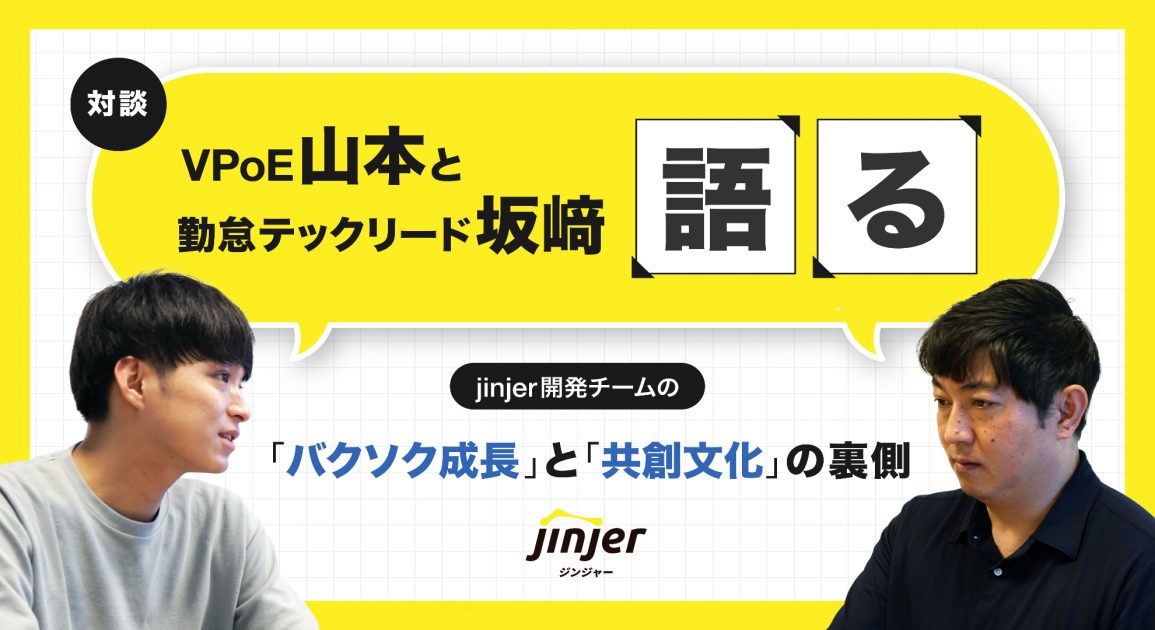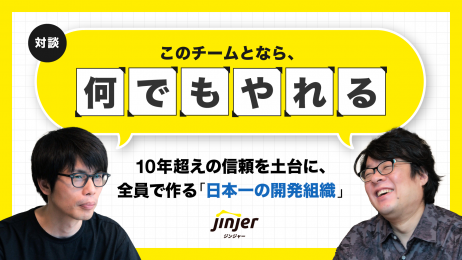企業の成長を支えるクラウド型人事労務システム「ジンジャー」。
今回は、その開発を牽引するVPoEの山本さんと、ジンジャー勤怠のテックリードを務める坂﨑さんにお話を伺いました。
新しい技術への挑戦、メンバーの意見がしっかりと反映される文化、そして驚異的な開発スピードの裏側について、深掘りします。
プロダクトと組織が織りなす「今が一番面白い」成長フェーズ
――坂﨑さんは昨年4月にjinjerにジョインされ、現在はジンジャー勤怠のテックリードを務めていらっしゃいますが、普段はどのような役割を担っていますか?
坂﨑: 勤怠システムにおいて一番大事な「集計」を核としつつ、そこからブレイクダウンして必要な機能を開発していくためのリードをしています。具体的には、技術選定、検証、アーキテクチャの設計、コードレビュー、チームメンバーの指導といった部分ですね。
HR Tech領域の中でも「勤怠」は特に複雑性が高く、深いドメイン知識が求められるため、責任を持って日々チームの皆と開発業務に勤しんでいます。
――山本さんは、VPoEとして普段はどのような役割を担っていますか?
山本:私はVPoEとして、エンジニア組織のマネジメントやプロダクトのグロースに関わる業務を担っています。
――坂﨑さん視点で、jinjerで働く上での魅力を教えてください。
坂﨑: 経験や年数に関わらず、積極的に挑戦をサポートしてくれる環境に、魅力を感じています。
テックリードという役割にかかわらず、周りのメンバーが意欲的に取り組んでいる姿を見ると、自発的に学び、「自分も成長し続けなければ置いていかれるかもしれない」という、良い意味での緊張感があります。
組織として学ぶための土台がしっかりしているからこそ、役職にかかわらず個人がさらに高みを目指せる環境だと感じています。

―― 山本さんは、VPoEとして現在の開発組織をどのように見ていますか?jinjerの成長フェーズについても教えてください。
山本: 今は、プロダクトとしても開発組織としても、ものすごく面白い時期だと思いますね。
ちょうど2年前は、正直なところ停滞期に近い状態だったんです。
以前のヒエラルキー型組織を根本から見直し、「ティール型組織」として、ひたすら課題と向き合い続けてきました。
その結果、メンバーが増え、ディスカッションが活発になり、さまざまな知識や経験がぶつかり合うことで、新しいものが生まれる土台ができたと感じています。
また、組織体制が整ってきたからこそ、メンバー単位でも、新しい技術やこれまでの経験にない領域に挑戦できる機会が格段に増えています。
例えば、これまでPHPをメインに開発していたエンジニアがGoに挑戦し、自発的に習得できるようになったこともその一つです。
「他社ではなかなかできない経験なので、やりがいがある」と、メンバーからの声があがっていて、新しい技術に次々と挑戦していけることは、社内で評価されるだけでなく、エンジニアとしての市場価値を高めることにも繋がっていると思います。
他にも、AIツールの導入により、開発業務と自動テストのスピードアップを実現しました。現状ではAIが生成する成果物の完成度が100%ではないため、開発時の設計やレビュー、そして作成されたプログラムの確認には人の手による品質向上が不可欠であり、この点についてはまだ道半ばです。
しかし、AIが「ゼロから作成する」部分を担うことで、私たちは設計やレビューを通じてプロダクトの品質向上にかけられる時間が増えました。この変化は、開発プロセスの非常に良い動き方であると実感しています。

並外れた開発スピードの秘密は、「共創」と「課題解決への飽くなき探求」
――「通常ではなし得ないようなスピードで開発をされている」と、CTO高村さんから伺いました。具体的にどのようなエピソードがありますか?
坂﨑: 開発中のプロダクトがまさにそうですね。非常に難易度の高いプロダクトで、これまでのジンジャーには導入されていなかったようなアーキテクチャを積極的に取り入れています。
ポイントは、「テックリードである私だけで意志決定をしていないこと」です。
チームメンバー全員で、「何を実装すべきか/しないべきか」をたくさん議論します。議論の末、意思決定してから実装に移るまでのスピード感はとても早く、これまで他社の開発組織では、経験し得なかった事だったので、とても刺激的で面白いなと実感しています。
山本: 定量的にも開発スピードは向上しています。
以前は、ヒエラルキー型組織だったこともあり、場当たり的な意思決定が多く、何が不足していて何を実装すべきかが不明確な時期がありました。
しかし、今は「何を決めなければならないか」が明確になり、KLOC(コード行数)の増加にも表れているように、実装量が飛躍的に増えています。これは、開発チーム全体で課題解決に対する共通認識が深まっており、無駄のない開発プロセスが確立されてきた証拠だと思います。

――「より良いプロダクト」を生む、開発組織体制とは?そのポイントを教えてください。
坂﨑: 先述したように、私がテックリードだからといって、一人で全てを決定するわけではありません。
むしろ、「このプロダクトをより良くするにはどうすればいいか?」という視点を常に持ち、チーム全員で議論し、納得した上で物事を進めることを最も大切にしています。
特に、経験者が少ない”新しい技術”に挑戦する際には、習得に時間がかかっても、皆で学び、試行錯誤しながら進めています。ホワイトボードを使って活発に意見を交わし、プロダクトに反映させるプロセスは、jinjerの開発組織ならではの魅力だと感じています。普通なら、一人で決めるか、決定までのプロセスがもっと長いものだと思います。
山本: 全員で一緒に学び、同じレベルで議論できるようになることで、開発できる領域も広がり、結果としてエンジニア個々人としての市場価値も向上します。
これは、組織としての成長と個人の成長が密接にリンクしているというjinjerの開発チームの強みです。
―― チーム全体の成長を加速させるために、他に意識していることはありますか?
坂﨑: SE全体で週に一度、特定のテーマについてグループディスカッションを行う場を設けています。
これは、メンバー全員が興味を持って自発的に参加できるようなテーマ設定を意識しており、効率的かつ楽しく、意欲的に成長できることを目的としています。皆で成長する喜びを分かち合うことが、jinjerが「日本一の開発組織」を目指せる理由だと思っています。
山本: 私たちは、「成長し続けること」=「課題を解決し続けること」だと考えています。課題は決してマイナスではありません。むしろ成長のための原動力です。このサイクルを回し続けることで、組織は常に進化し続けることができます。
メンバー一人一人がこの意識を持って、開発に臨めるように、VPoEとして、サポートするようにしています。
「jinjer社でしかできない経験」が、あなたの市場価値を高める
――最後に、jinjerの開発チームに興味を持つ候補者の方へメッセージをお願いします。
坂﨑: jinjerでは、経験年数やスキルレベルに関わらず、誰もが意見を出しやすく、それがプロダクトに反映されやすい文化が根付いています。
ドメイン知識がない方も、業務の中でOJTとして、あなたの経験やスキルに合わせて習得をサポートします。一人に任せて「やってみて」という文化ではないので、ご安心ください。
山本: jinjerは、一人のエンジニアにすべてを任せきりにするような文化ではありません。皆で一緒に悩み、考え、解決していく「共創」の精神が息づいています。
多角的な視点から課題にチャレンジできる環境があり、その過程で誰もが成長できる。そうして得た経験は、必ずあなたの市場価値を高めることにつながると思います。
開発組織だけでなく、会社全体として共に成長していける、そんな仲間を心から求めています。「日本一の開発組織」を一緒に作り上げていきましょう。

まとめ
jinjerの開発チームでは、自律的な成長意欲を持ち、チームで課題解決に取り組むことを楽しめるエンジニアを歓迎しています。新しい技術への挑戦、自身の意見がプロダクトに反映される喜び、そして圧倒的なスピード感の中で成長できる環境に魅力を感じた方は、ぜひ一度カジュアルにお話しましょう!
▽カジュアル面談のご応募はこちらから
https://jobs.jinjer.co.jp/position/
▽テックブログはこちらから(毎月更新しています!)
https://zenn.dev/p/jinjer_techblog